| 御覧になりたい写真をクリックすると拡大されます |

|
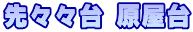
昭和3年11月に昭和天皇の即位の儀などの
「御大典」を祝って原屋台が
奉納された際の写真です。
この屋台は、原・本村在住の大工さん、
指物屋さんなどの職人さんが
手作りされた屋台で、昭和8年に
原が灘の宇佐崎から神輿屋根屋台を購入後に
志方まちの下之町に売却されました。
屋台が据えられているのは、
県道65号線の旧藤城理容所付近です。
(写真提供:原・本村/Hさん)
|
 |
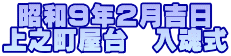
新調入魂式とあって、梵天(海老)や狭間は、
まだついていないようです。
昭和8年の秋、姫路の灘のけんか祭りを見物に
行った村の青年団数人が、屋台の製作をしていた
白浜の麦本政雄工場に出向き、製作途中だった
この反り屋根布団屋台を、村に一切相談なく
「これ買うわ」と、僅かな手付金を置いて
勝手に屋台購入を契約。
翌1月の上之町の新年会の冒頭で、
「すみません買うてまいました、来月納品です」と
土下座をして、発覚したことから、村は大慌てで
昭和8年12月末に、現在の上皇陛下が
御降誕されたことで「皇太子殿下御降誕記念」と
称し御花を集め屋台蔵から建設をしたりと大騒動で
入魂式後のお披露目練りで御花を出し渋った
近隣の村の家には、新調屋台で本棒突きを敢行して
門を木っ端微塵に破壊するなどして
お祝いムードとはかけ離れた破茶滅茶な入魂式で
近隣の村の人々を恐怖で震え上がらせたと
古老が話しておられました。
昭和29年、この屋台を西脇市南本町に売却した
資金で、旧上之町公会堂が建設されたことを
風化させないように、旧と新しい上之町公会堂にも
この写真を大きく引き伸ばしたものが
掲げられてしますが、
その写真の意味するものを知っている人は、
ほとんどいなくなってしまいました。
尚、西脇市南本町では、この屋台を今でも大切に
改修を繰り返しながら
秋祭りに奉納されておられます。
(写真提供:元 上之町屋台 乗り子
上之町:Hさん)
|
 |
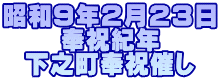
写真裏には
「昭和9年2月23日 奉祝紀年
下之町奉祝催し」
と書いてあります。
この屋台は、上記にある昭和3年の
御大典の際に原・本村の大工・指物屋などの
職人さんが手作りされた屋台で、
原が灘の宇佐崎から神輿屋根屋台を購入後に
志方まちの下之町が購入しました。
写真中央に、後に志方町長をされる
藤本 和蔵氏の若かりし頃の姿が写っています。
(写真提供:下之町/ Nさん)
|

|
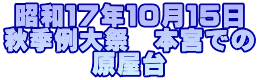
写真裏には
昭和壱拾七年拾月拾五日 寫ス 秋祭催 屋台
と、書かれてあります。
「こばた」の看板から原屋台があるのは、
現在の県道65号線 原交差点のど真ん中と
思われます。
戦時中であったのにもかかわらず、
着物で着飾っている女性が印象的です。
(写真提供:原・本村/ Kさん)
|
 |
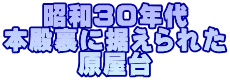
屋台の後ろに鐘撞堂が写っていることから
宮入り後に本殿の裏に据えられた
原屋台の写真です。
屋台紋が横龍紋になっているのが、
よくわかります。
通常、神輿屋根屋台では
龍紋などは屋台の前後で、
神社神紋の巴紋が左右につけられますが、
原地区では、屋台の前に御幣をつけるので
「せっかく立派な龍紋が御幣で見えない」と
いう理由から、敢えて横龍紋にしていたと
古老より伺いました。
昭和30年代に撮影された
写真とのことです。
(写真提供:原・本村/ Yさん)
|
 |
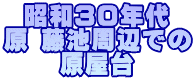
原の大屋台の勇姿です。
太鼓打ちなど人物の大きさから比べると、
非常に大きな屋台です。
正面に写っている眼鏡の男性が着ている
かすりの法被が
原若連中の正式なものとのことです
原の藤池地区のあたりで
撮影された写真とのことです。
(写真提供:原・本村/Yさん)
|
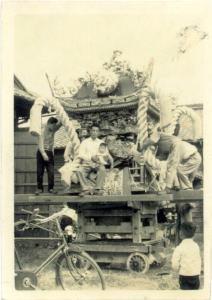 |
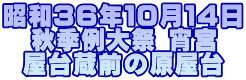
写真の裏に
S36 10 14 H(実名)パパにだっこして
と書かれていました。
昭和36年10月14日の原屋台蔵のある
原・本村公会堂前の原屋台です。
かつて当宮の秋祭りは、
10月14日・15日に行われていたので
宵宮の日に撮影された
写真ということになります。
写真撮影の横で、ヤッサ役員と思われる方が
伊達綱を取り付けているように見えます。
宵宮の出立ち前でしょうか?
(写真提供:原・藤池/ I さん)
|
 |

写真裏に「S39 10 15」とあります。
昭和39年10月15日の
当宮秋季例大祭の本宮の日に
撮影されたと思われる
屋台蔵&原・本村公会堂前の原屋台です。
太鼓の鏡面2尺5寸は、浜手の太鼓としては
やや小ぶりですが、宇佐崎にあった時には、
家島まで響くと言われていたほど、
よく鳴る太鼓だったそうです。
原地区でも、御花を出し渋る家があると
その家の前に屋台を据えて太鼓を打ちまくり
太鼓の爆裂音と振動で、家の屋根瓦が
ズリ落ちて来るほどで、みんな大慌てて
御花を出したという伝説が残っています。
(写真提供:原・藤池/ Iさん)
|
 |

写真裏には、何も書かれていませんでしたが
上記の「S39 10 15」と書かれた
写真と一緒にあったようなので、
同じ日に撮影されたものと考えられます。
昭和39年と言いますと、
10月10日に東京オリンピック開会式が
行われた年ですので、
この写真は、東京オリンピックの開会式の
5日後の写真ということになります。
(写真提供:原・藤池/ Iさん)
|


|
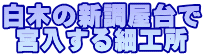
細工所屋台は昭和62年に新調されました。
秋季例大祭直前の屋台購入だったとのことで
錺金具が間に合わず、仮の総才端を取り付けて
宮入したとのことです。
(写真提供:細工所屋台保存会/ I さん) |


|
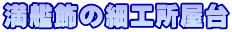
細工所屋台は昭和62年に新調され
翌昭和63年に錺金具が取り付けられ、
今では珍しい白木屋根に錺金具がつけられた
満艦飾になっている写真です。
水引幕や高欄掛が現在の物と違い、
仮のものになっています。
伊達綱も現在は太くなっていて、
写真の旧伊達綱は、現在の原屋台で
使用されています。
(写真提供:細工所屋台保存会/ I さん)
|

|
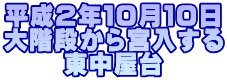
平成2年10月10日秋季例大祭・本宮にて
大階段から勇壮に宮入する東中屋台。
東中屋台は、数回しか宮入しておらず、
非常に貴重な写真です。
(写真提供・中之町 Fさん)
|

|
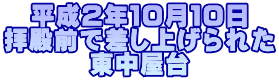
平成2年10月10日秋季例大祭・本宮にて
拝殿前で豪快に差し上げられた東中屋台。
(写真提供・中之町 Fさん)
|



|
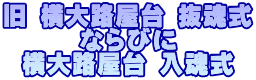
平成24年 7月 吉日
横大路公会堂横の屋台蔵にて
横大路が新たな屋台を購入され
長年親しまれた旧横大路屋台の抜魂式と
新たな屋台に魂を入れる入魂式が
執り行われました。
|


|
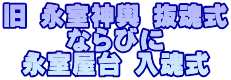
平成24年 9月25日
永室公会堂南の広場にて
長年親しまれた旧永室神輿の抜魂式と
新たに購入された屋台の入魂式が
行われました。
旧永室神輿は、屋根の漆塗替や総メッキなど
大修理を施され、現在も養父方面の村で
活躍しているとのことです。
(写真提供:永室・えがお介護タクシーさん)
|


|
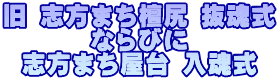
令和元年 7月14日
志方まち屋台蔵裏にある上之町公会堂前にて
昭和50年代中頃から親しまれて来た
旧志方まち檀尻の抜魂式と
新たに購入された志方まち屋台の入魂式が行われ
お祓いの後、新しい屋台が豪快に
差し上げられました。
旧志方まち檀尻は、氏子の中の賑わい物の中で
唯一の檀尻でありましたが、
鳴りが自慢の下之町の太鼓を載せて
旧上之町大屋台の乗り子を務められた
太鼓名人指導の下、昭和29年の屋台売却と共に
一度は途絶えてしまった
上之町伝統の「絶やさずの太鼓」を復活させ
伝統を繋いだという意味で、
非常に大きな役割を果たしました。
|


平成26年 太々(国恩祭)での
永室屋台の雄姿
|
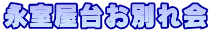
令和5年7月22日(土)
少子化による乗り子(太鼓打ち)と
高齢化による練り子不足に加え、
新型コロナウィルス感染症がトドメを刺し
平成24年の秋祭り以降、親しまれて来た
永室屋台が、その役目を終え
たくさんの村人に見送られて
業者に引き取られて行きました。
永室の屋台は廃絶してしまいましたが、
屋台を購入した平成24年の秋季例大祭での
初めての宮入の際、
大階段を掛け登った直後に屋台を差し上げ、
そのまま拝殿前まで進んでの豪快な宮入や、
平成26年5月の太々(国恩祭)での
連戦連勝の練り合わせなど、
地蔵盆踊り法会の太鼓巡行で肩を馴らした
永室にしか出来なかったであろう伝説の数々は
今後も志方の祭りの中で
末永く語り継がれていくことでしょう。
(写真提供:永室・えがお介護タクシーさん)
|

志方八幡宮や昔の屋台・獅子舞・胡蝶の舞、
秋祭りや国恩祭(だいだい)など、
古い写真をお持ちの方がおられましたら
是非、こちらまで  で、御連絡下さい。
メール
|

